最近は「心付けは不要です」と明言する葬儀社も多く、かえってどうすれば良いか戸惑う場面もあります。
この記事では、そんな葬儀の心付けの疑問や渡す相手別の相場から、いざという時に慌てない封筒の書き方、そして「葬儀で心付けはいらない」と言われた時の対応まで丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたの心付けに関する不安が解消され、心から納得のいく形で感謝を伝えられるようになっているはずです。
葬儀の「心付け」とは?
葬儀における心付けとは、葬儀でお世話になったスタッフの方々へ、正規の料金とは別に、感謝の気持ちとして個人的にお渡しするお金や品物のことを指します。欧米の「チップ」と似ていると感じるかもしれませんが、少しニュアンスが異なります。
チップがサービスに対する半ば義務的な対価であるのに対し、心付けはあくまでも「お世話になりました」「本当にありがとうございます」という、遺族からの自発的な感謝の気持ちが主体です。ですから、必ず渡さなければならないという厳密なルールはありません。
この習慣は、かつて葬儀を地域社会の共同体で執り行っていた時代の名残とも言われています。当時は、ご近所の方々や親戚が役割分担をして葬儀を手伝っていました。
その際、喪主が「お世話になりました。これで疲れを癒してください」と、労いの意味を込めてお金や酒肴を渡したのが始まりとされています。
時代が変わり、葬儀のプロである葬儀社が一切を取り仕切るようになった現代でも、滞りなく式を進めてくれたスタッフへの感謝の気持ちを表す方法として、この「心付け」という習慣が残っているのです。
江戸時代には、葬儀の費用が高額であったため、葬儀に関わった人々への報酬として、心付けが重要な役割を果たしていました。
心付けを渡す相手と金額相場
具体的に心付けは「誰に」「いくらくらい」渡すのが一般的なのでしょうか。もちろん、これはあくまで目安であり、地域性や葬儀の規模、お世話になった度合いによって変動します。感謝の気持ちを表すものですから、無理のない範囲で準備することが大切です。
| 担当者(スタッフ) | 金額相場 | 補足・ポイント |
|---|---|---|
| 葬儀の担当者(責任者) | 5,000円~10,000円 | 葬儀全体の中心人物。他のスタッフ分もまとめてお渡しする ことが多い、最も手厚く包む相手です。 |
| アシスタント(式典スタッフ) | 3,000円~5,000円 | 当日の会場設営や参列者案内などを担当。複数名いる場合は、 代表者にまとめて渡すのがスマートです。 |
| 司会者 | 3,000円~5,000円 | 心に残るお別れを演出してくれた司会者個人へ、 感謝の気持ちとしてお渡しすることがあります。 |
| 湯灌(ゆかん)・納棺スタッフ | 5,000円~10,000円 | 故人を清め旅立ちの支度をする専門職。故人を丁寧に 扱ってくれたことへの深い感謝を込めて渡します。 |
| 霊柩車の運転手 | 3,000円~5,000円 | 故人を火葬場まで大切に運んでくれる運転手へ、 感謝と労いを込めて渡します。 |
| マイクロバスの運転手 | 3,000円~5,000円 | 親族や参列者を送迎するバスの運転手へ。 長時間の運転に対する労いの気持ちです。 |
| 火葬場の職員 | 3,000円~5,000円 | 【重要】 公営の火葬場は公務員にあたるため、受け取りを 固く禁止している場合がほとんどです。 |
| 料理の配膳スタッフ | 3,000円~5,000円 | 通夜振る舞いや精進落としの担当。責任者に 「皆様で」とまとめて渡すのがスマートです。 |
このように、葬儀には本当に多くの方が関わってくださいます。全員に渡すのは大変ですし、現実的ではありません。基本的には、窓口となってくれた葬儀の担当者に「皆様でどうぞ」とまとめてお渡しするのが、最もスマートで負担の少ない方法と言えるでしょう。
僧侶への心付け:お車代とお食事代

お車代の金額相場
僧侶には、葬儀の際に、読経や法話などを行っていただきます。そのため、僧侶には、お車代として心付けを贈ることが一般的です。
お車代の金額は、僧侶の宗派や寺院の規模、葬儀の規模によって異なりますが、一般的には、数千円から数万円程度が相場です。近年では、お車代は、現金ではなく、商品券やギフト券で贈るケースも増えています。
お食事代の金額相場
僧侶には、葬儀の際に、食事を提供することもあります。そのため、僧侶には、お食事代として心付けを贈ることが一般的です。
お食事代の金額は、僧侶の宗派や寺院の規模、葬儀の規模によって異なりますが、一般的には、数千円から数万円程度が相場です。近年では、お食事代は、現金ではなく、商品券やギフト券で贈るケースも増えています。
「葬儀で心付けはいらない」が主流?その背景と理由
現代では「葬儀で心付けはいらない」という考え方が主流になりつつあります。多くの葬儀社が、公式ホームページやパンフレットで「心付けや付け届けは一切ご辞退申し上げます」と明記しています。
最も大きな理由は、料金体系の明確化です。かつての葬儀費用には不明瞭な部分もありましたが、現在では必要なサービス料がすべて含まれた「プラン料金」が一般的になりました。これにより、消費者は追加費用の心配なく安心して依頼できるようになっています。
また、企業コンプライアンスの観点から、社員が直接金品を受け取ることを社内規定で禁止する葬儀社も増えました。これは、心付けの有無でサービスに差が出る懸念や金銭トラブルを防ぐための措置です。
さらに、こうした方針は、精神的・経済的に大きな負担を抱える喪主様への配慮でもあります。心付けのことで悩ませることなく、故人様とのお別れそのものに集中してほしいという想いが、「心付け不要」という現代の葬儀の形を後押ししているのです。
「心付けは不要です」と言われたら?
葬儀社の担当者に「お心遣いはご辞退しております」と明確に伝えられた場合、無理に渡そうとしないことです。
「そう言わずに…」と無理強いするのは、相手を困らせてしまい、かえって失礼にあたります。会社のルールを破らせてしまうことにもなりかねません。
しかし、「それでも、この感謝の気持ちをどうにかして伝えたい!」と思うのは当然のことです。現金(心付け)以外にも、感謝を伝える方法はたくさんあります。
1. 心からの感謝の言葉を伝える
何よりも嬉しいのは、心のこもった感謝の言葉です。葬儀が滞りなく終わった後、担当者の方に直接、次のような言葉を伝えてみてはいかがでしょうか。
「〇〇さんのおかげで、父も喜んでいると思います。本当に温かいお見送りになりました。心から感謝しています。」
「何もわからない私たちに、親身に寄り添ってくださって本当に助かりました。ありがとうございました。」
具体的なエピソードを交えて伝えると、より気持ちが伝わります。あなたの言葉が、スタッフにとって何よりの励みになるはずです。
2. アンケートやお客様の声に記入する
葬儀後に、葬儀社からアンケートや「お客様の声」への協力を依頼されることがあります。もし心の底から満足のいくお見送りができたなら、ぜひ協力してあげてください。
そこにお世話になったスタッフの名前を挙げ、「〇〇様には大変お世話になりました。細やかな気配りに家族一同、感謝しております」といった具体的な賛辞を書き添えるのです。これは、葬儀担当者へのお礼として非常に効果的です。
お客様からの評価は、社内でのそのスタッフの評価に直結し、ボーナスや昇進に繋がることもあります。現金よりも喜ばれる、素晴らしい「お礼」の形です。
3. 菓子折りなど品物で渡す
現金は辞退されても、菓子折りなどの「消え物」であれば受け取ってもらえる場合があります。ただし、これも会社の方針によりますので、事前に確認するのが無難です。
もし渡す場合は、以下のような点に配慮するとよいでしょう。
• 高価すぎないもの:相手に気を遣わせない3,000円~5,000円程度のものが目安です。
• 個包装になっているもの:スタッフ全員で分けやすいようにします。
• 日持ちするもの:すぐに食べきれなくても安心です。
• 渡すタイミング:葬儀が終わり、少し落ち着いたタイミングで「皆様で召し上がってください」と一言添えて渡します。
4. 後日、お礼状を送る
葬儀から数日後、落ち着いてからお礼状を送るのも非常に丁寧な感謝の伝え方です。手書きの手紙は、より一層気持ちが伝わります。形式ばったものでなくても構いません。葬儀でお世話になったことへの感謝の気持ちを、ご自身の言葉で綴ってみましょう。
このように、「心付け=現金」と固く考えず、様々な形で感謝を伝えることができます。
葬儀の心付けを入れる封筒の書き方と選び方
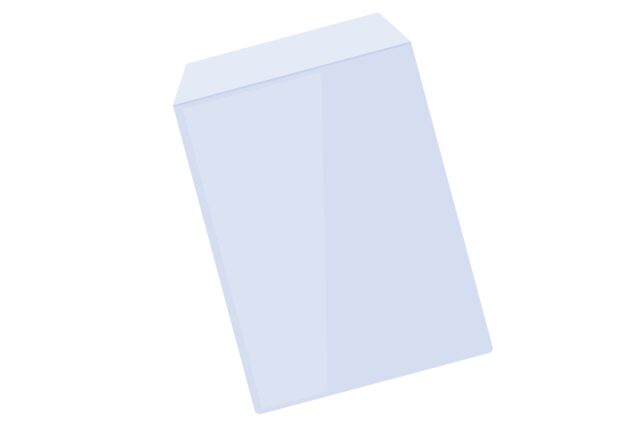
封筒の選び方
心付けを入れる封筒は、白無地の封筒を選びましょう。一般的には、角2封筒が使用されます。
封筒の材質は、厚手のものや、金封のような高級感のあるものが好ましいです。また、封筒の表書きには、相手の名前や肩書きを丁寧に書きましょう。
白や双銀の水引がついた不祝儀袋(香典袋)は、故人へのお悔やみの気持ちを表すためのもので使用しません。
表書きの書き方
封筒の表面中央に、毛筆や筆ペンで目的を書きます。この時、香典とは違って薄墨ではなく、濃い墨で書くのがマナーです。薄墨は「涙で墨が薄まった」「急なことで墨をする時間がなかった」というお悔やみの気持ちを表すもの。心付けは感謝の気持ちですから、濃い墨ではっきりと書きましょう。
一般的な表書きは以下の通りです。
• 「御礼」:最も一般的で、誰に対しても使える丁寧な表書きです。迷ったらこれを選べば間違いありません。
• 「志」:「感謝のしるし」という意味で、こちらもよく使われます。「志」は宗教宗派を問わず使える便利な言葉ですが、地域によっては香典返し(満中陰志など)の表書きとして使われることが多いため、「御礼」の方が誤解を招きにくいかもしれません。
• 「心付け」:文字通り心付けであることが伝わりますが、少し直接的で、目上の方から目下の方へ渡すニュアンスに受け取られることもあります。葬儀社の担当者などへは「御礼」の方がより丁寧な印象になります。
名前の書き方
表書きの真下に、少し小さめの文字で差出人の名前を喪主のフルネームで書きます。名前の代わりに「〇〇家」と家名を書いても構いません。
裏面の書き方
心付けの封筒の裏面には、基本的に住所や金額は書かなくても良いとされています。これは、相手に記録されたり、返礼の気を遣わせたりしないための配慮です。
どうしても誰からのものか分かるようにしたい場合は、左下に住所と氏名を書いても構いませんが、金額は書かないのがマナーです。
お札の準備と入れ方のマナー
お札は新札を避けるのが望ましい
香典では「不幸を予期して準備していた」と受け取られるのを避けるため、新札を使わないのがマナーとされています。心付けの場合、これはお悔やみではないため、新札でも問題ないという考え方もあります。
しかし、葬儀という一連の流れの中で渡すものですから、香典と同様に新札は避け、きれいな旧札(使用感のあるお札)を使うのが無難で、より丁寧な印象を与えます。
もし手元に新札しかない場合は、一度二つに折り目を付けてから封筒に入れると良いでしょう。この一手間が、相手への配慮として伝わります。ボロボロのお札やシワだらけのお札は失礼にあたるので、避けてください。
お札の入れ方・向き
お札を封筒に入れる際の向きにもマナーがあります。
• お札の肖像画(顔)が、封筒の表側(表書きが書いてある面)を向くように入れます。
• お札の肖像画が、封筒の入り口側(上側)に来るように入れます。
複数枚入れる場合は、すべてのお札の向きを揃えてから封筒に入れましょう。これはお祝い事のご祝儀と同じ入れ方で、「喜び」や「感謝」といった上向きの気持ちを表すものです。
封筒にお金を入れたら、封はしなくても構いません。ただし、中身が出てしまわないか心配な場合は、シールなどで軽く留めても良いでしょう。
心付けを渡す最適なタイミングと渡し方

心付けを渡すタイミング
心付けを渡すタイミングは、葬儀社の担当者や火葬場のスタッフには、葬儀が終わった後に、直接渡すか、香典と一緒に渡すのが一般的です。
手伝ってくれた方々には、葬儀が終わった後に、直接渡すか、後日改めて渡すのが一般的です。僧侶には、葬儀が終わった後に、お車代とお食事代を別々に渡すのが一般的です。
渡し方の作法
直接手渡しするのではなく、小さなお盆や菓子折りの上に乗せて渡すと、より丁寧な印象になります。もちろん、それが難しい場合は手渡しでも問題ありません。
その際は、相手から見て表書きが読める向きで差し出し、「ほんの気持ちですが、皆様で召し上がってください」「大変お世話になります。よろしくお願いいたします」など、感謝や労いの言葉を一言添えましょう。無言で差し出すのは避けてください。
地域によって違う?心付けの習慣
例えば、都市部では「心付け不要」がスタンダードになりつつある一方で、地方や古くからの慣習が根強く残る地域では、今でも心付けを渡すのが当たり前とされている場合があります。また、渡す相手や金額の相場も、その土地ならではの基準があるかもしれません。
るのが一番です。もちろん、葬儀社の担当者に「このあたりでは、皆様どうされていますか?」と率直に尋ねてみるのも良いでしょう。きっと、適切なアドバイスをくれるはずです。
まとめ
葬儀という非日常の中では、ささいなことでも「これで合っているのだろうか」と不安になってしまうものです。しかし、心付けで最も大切なのは、高価な金額や完璧な作法ではありません。
「おかげさまで、心温まる良い式になりました。本当にありがとう」
その純粋な感謝の気持ちこそが、故人の旅立ちを支えてくれた方々への最高のお礼になるはずです。この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、心からの感謝を伝える一助となれば幸いです。

