初めて葬式に参列する際、服装だけでなく供える花にも気を配る必要があります。特に「白い花がよいと聞くけれど本当?」「洋花や胡蝶蘭はダメなの?」と不安になる方も多いでしょう。
この記事では、葬式にふさわしい花の種類やマナーを丁寧に紹介し、供花の相場についても解説します。これを読めば、安心して選べるようになるはずです
葬式にふさわしい花の種類は?基本は白を基調とした落ち着いた花
葬式に供える花は、故人への哀悼の意を表すものであり、派手さや華美さを避けるのが基本です。もっともふさわしいとされるのは、白を基調とした落ち着いた花です。白は「清浄」「無垢」を象徴し、宗教や地域を問わず受け入れられやすい色とされています。
実際の葬儀では、菊や百合など白い花が中心となることが多く、淡いピンクや薄紫といった控えめな色を加える場合もあります。
ただし、赤や濃い色合いの花は「お祝い」を連想させるため不適切とされます。参列者が個別に供花を選ぶ際も、落ち着いた色合いを意識すると安心です。
例えば、関東地方の一般的な葬儀では白と薄紫の菊を組み合わせた供花が多く見られます。関西地方では白菊に加え、淡い黄色の小菊を混ぜることもあります。地域性はあるものの、いずれも「落ち着き」と「清潔感」を大切にした選び方が基本です。
葬式に供える花の種類と特徴
葬式に用いられる花にはいくつかの代表的な種類があり、それぞれに特徴や意味があります。ここでは主な花について解説します。
代表的な花:菊・百合・カーネーション
葬儀で最も多く使われるのは菊です。菊は「高潔」「真実」を象徴し、長持ちするため供花に適しています。白菊が中心ですが、淡い黄や薄紫も使用されることがあります。
百合は「純粋」「威厳」を表す花で、香りが強いため大きな祭壇や会場に用いられることが多いです。特にカサブランカの白百合は豪華さと清らかさを兼ね備えています。
カーネーションは「無垢な愛」を象徴し、母の日の花として知られていますが、葬儀でも白や淡い色がよく用いられます。花持ちがよく、アレンジメントにも適しています。
お通夜でよく選ばれる花
お通夜では急ぎで供花を手配することが多いため、扱いやすく落ち着いた花が選ばれます。白菊や小菊は手配しやすく、アレンジもしやすいことから定番です。また、地域や慣習によっては洋花を控える場合もありますが、最近は淡い色のカーネーションやスプレーマム(小菊の一種)が使われることも増えています。
胡蝶蘭や洋花を用いる場合の注意点
胡蝶蘭は「幸福が飛んでくる」という意味を持つため、慶事に用いられることが多い花ですが、近年は葬儀の場でも白の胡蝶蘭が選ばれることがあります。ただし、地域や宗派によっては不適切とされることもあるため注意が必要です。
洋花(バラやガーベラなど)は華やかすぎる印象を与える場合があるため、基本的には避けるのが無難です。どうしても洋花を使いたい場合は、白や淡い色を選び、アレンジ全体を落ち着いた雰囲気に仕上げることが大切です。
葬式でダメとされる花の種類と理由
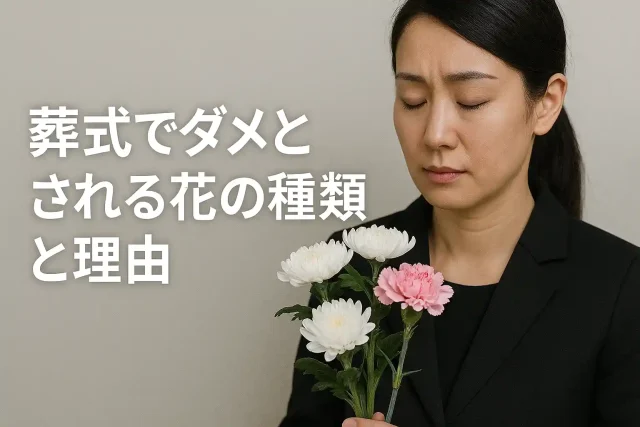
葬式の花は「故人を悼み、遺族に寄り添う気持ち」を表すものです。そのため、選ぶ花の種類や色には細やかな配慮が必要です。特に以下のような花は、不適切とされるため注意しましょう。
トゲのある花や香りが強すぎる花
バラやアザミなどトゲのある花は、「痛み」や「争い」を連想させるため葬儀には向きません。また、強すぎる香りを放つ花(ユリの一部品種や濃い香りの洋花)は、参列者に不快感を与える可能性があります。特に閉じた式場では香りが充満しやすいため、強香の花は避けるのが無難です。
赤や派手な色合いの花
赤は「情熱」「祝福」を意味し、結婚式や祝い事ではふさわしい色ですが、葬儀では場にそぐわないとされています。赤いバラや真っ赤なガーベラなどは避けましょう。
また、ビビッドなピンクやオレンジといった派手な色合いも「華やかさ」が強調されるため不適切です。葬儀では白を基調とし、淡い紫や薄い黄色など控えめな差し色にとどめるのが安心です。
日持ちがしない花や季節外れの花
供花は通夜から葬儀・告別式まで数日間飾られることも多いため、日持ちのしない花は適しません。例えば、ひまわりやチューリップは水が下がりやすく、花がすぐにしおれてしまうため不向きです。
また、季節外れの花を無理に選ぶと「慶事用に温室で栽培された花」と見なされ、違和感を与えることがあります。旬の花を選ぶことで自然で落ち着いた印象を保つことができます。
実際の例として、関東地方では「白菊中心の落ち着いたアレンジ」が好まれる傾向がありますが、関西では地域によって黄色や薄紫を差し色にすることもあります。いずれの場合も、派手さや不適切な種類を避けるのが共通のマナーです。
こうした「ダメとされる花」の知識を持っておくことで、供花を選ぶ際に迷わず判断でき、遺族に対しても誠意のある対応ができるでしょう。
供花を選ぶ際に押さえておきたいポイント
供花を選ぶときには、単に「きれいな花を贈る」だけでは不十分です。宗教や宗派、地域の慣習、さらに遺族の意向を尊重することが大切です。ここでは特に注意したい3つの視点を紹介します。
宗教・宗派ごとの違い
仏教では白菊を中心に、百合やカーネーションなど落ち着いた花がよく用いられます。ただし、浄土真宗では「死を穢れとしない」考えから、明るめの花を加える場合もあります。
キリスト教の場合は白い百合やカーネーション、洋花を中心にしたアレンジが一般的です。一方、神道では榊(さかき)を供える習慣があり、花を贈る場合も白や緑を基調としたシンプルなものが望まれます。
このように、宗教・宗派によって花の種類や色の選び方が変わるため、事前に確認しておくと安心です。
遺族の意向や地域の慣習を尊重する
供花の種類やスタイルは、地域ごとに違いがあります。関東では「白菊を中心としたアレンジ」、関西では「白に加えて淡い紫や黄色を組み合わせる」などがその例です。
地域性を知らずに派手な花を選んでしまうと、遺族や参列者に違和感を与える可能性があります。
また、最近では「生花ではなくプリザーブドフラワーを望む」「供花は辞退したい」という遺族の意向が示されるケースも増えています。
案内状や訃報に「供花はご遠慮ください」と記載がある場合は必ず従いましょう。供花は「遺族を思いやる心」が第一であることを忘れないようにしましょう。
個人で送る場合と会社から送る場合の違い
個人で供花を送る場合は、1基(スタンド花1台)を手配するのが一般的で、値段は1万円〜2万円程度が相場です。親しい間柄であれば、かご花やアレンジメントを選ぶこともあります。
一方、会社や団体から供花を送る場合は、見栄えを考慮して2基(対のスタンド花)を手配することが多く、費用は2万円〜3万円程度になります。札に会社名や部署名を記載することで、遺族に「組織としての弔意」を伝えることができます。
例えば、取引先の社葬や社員の葬儀に会社として供花を出す際は、他の企業や団体とのバランスも考慮し、担当部署や総務を通じて事前に確認するのが望ましいです。
これらのポイントを押さえることで、供花を選ぶ際に迷うことなく、遺族に失礼のない対応ができるでしょう。
葬式用の花の値段相場
供花を手配する際に多くの方が気になるのが値段です。葬式用の花は種類やスタイルによって相場が異なり、1万円前後から数万円まで幅があります。ここでは代表的な供花の種類ごとに目安を紹介します。
スタンド花の価格帯
スタンド花は祭壇の左右に飾られる大型の供花で、もっとも一般的な形です。価格帯は1基あたり1万5千円〜2万円が相場で、会社や団体からは2基(対)で注文するケースが多くなっています。
大きさや花の種類によって3万円程度になる場合もあります。スタンド花は見栄えが良く、多くの参列者が一目で「誰から贈られたか」を確認できるため、企業関係や団体で選ばれることが多いです。
籠花やアレンジ花の値段目安
籠花(かごばな)やアレンジ花は、籠や器に花をまとめた供花で、個人で贈る場合に選ばれることが多いです。
値段の目安は8千円〜1万5千円程度とスタンド花よりも手頃で、親族や親しい友人から贈られることが多い形式です。サイズは小ぶりでも、心を込めた供養の気持ちを十分に表すことができます。
特に遠方から参列できない場合に、インターネット注文でアレンジ花を手配する方も増えています。その際も「白を基調にした落ち着いたデザイン」を選ぶのが安心です。
お通夜と告別式での費用感の違い
供花は「お通夜から告別式まで飾られる」ことが一般的で、費用感に大きな違いはありません。ただし、葬儀社によってはお通夜と告別式の両日で花の追加や差し替えが行われる場合があります。その場合は1基あたりプラス5千円〜1万円程度の追加費用が発生することもあります。
また、地域によっては「お通夜だけに供花を飾る」「告別式から花を並べる」といった慣習の違いもあります。例えば、関西では告別式から供花を並べるケースが多い一方、関東ではお通夜の段階から飾ることが一般的です。どちらにしても、葬儀社に事前に確認しておくと安心です。
このように、供花の値段は種類や地域性、葬儀社の運営方法によって変わります。目安を把握しておくことで、予算を立てやすくなり、失礼のない形で故人を偲ぶことができるでしょう。
まとめ|葬式の花は「落ち着き・清潔感・故人への敬意」が基本
葬式に供える花を選ぶときの基本は、白を中心に落ち着いた色合いを用い、清潔感と故人への敬意を表すことです。菊や百合、カーネーションなどの定番の花は多くの地域や宗教で受け入れられやすく、安心して選べます。
一方で、赤や派手な色の花、トゲのある花、香りの強すぎる花は不適切とされるため注意が必要です。供花を選ぶ際には、宗教や宗派ごとの違い、地域の慣習、そして遺族の意向を尊重することが何より大切です。
値段については、スタンド花で1万5千円〜2万円前後、籠花やアレンジ花で8千円〜1万5千円程度が目安となります。会社から送る場合は2基を対で注文するなど、立場に応じた対応を心がけましょう。
葬式の花は単なる飾りではなく、故人を偲ぶ心を形にする大切な手段です。基本のマナーを理解し、落ち着きと清潔感を意識した花を選ぶことで、遺族に誠意が伝わり、安心して参列できるはずです。
