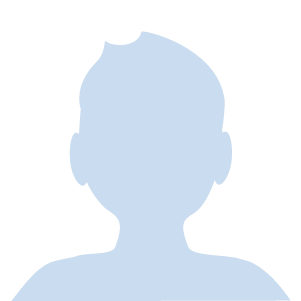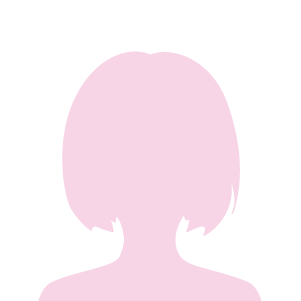大切なご遺骨に関わる書類だからこそ、その役割や手続きについて正確に知っておきたいですよね。
ご安心ください。実は「火葬許可証」と「埋葬許可証」は、もともと1枚の同じ書類です。手続きの段階に応じて、その呼び名と役割が変わるだけなのです。
この記事では、火葬許可証と埋葬許可証の根本的な違いから、一枚の紙が「埋葬許可証」になるまでの流れ、申請方法、そして万が一の紛失時の対処法まで、あなたが抱える疑問を一つひとつ解消していきます。
この記事を最後まで読めば、火葬から納骨までの一連の手続きを、不安なくスムーズに進められるようになるはずです。
火葬許可証と埋葬許可証の違いは
「火葬許可証」と「埋葬許可証」は、別々の書類ではありません。市区町村の役所で交付された「火葬許可証」に、火葬場で「火葬を執行しました」という証明の印が押されることで、その書類が「埋葬許可証」へと役割を変える仕組みになっています。
1. 役所で交付 → 火葬許可証(火葬するための許可証)
2. 火葬場で証明印が押される → 埋葬許可証(遺骨をお墓に納めるための許可証)
このように、1枚の書類がプロセスを経て呼び名が変わる、と理解しておけば大丈夫です。法律(墓地、埋葬等に関する法律)で定められた、故人様を適切に弔うために欠かせない非常に大切な書類なのです。
死亡届から埋葬許可証になるまでの流れ
「火葬許可証」を手に入れ、それが「埋葬許可証」になるまでの一連の流れを時系列で詳しくご説明します。
多くの場合、これらの手続きは葬儀社が代行してくれますが、ご自身で手続きをされる可能性もゼロではありません。全体の流れを把握しておくと、いざという時に落ち着いて対応できます。
1:市区町村役場へ「死亡届」を提出する

すべての手続きは、故人様の「死亡届」を役所に提出することから始まります。
何を提出する?
• 死亡届:医師が作成した「死亡診断書(または死体検案書)」と一体になった用紙です。左半分が死亡診断書、右半分が死亡届となっています。届出人が必要事項を記入します。
• 届出人の印鑑:シャチハタ以外の認印で問題ありません。
誰が提出する?
• 法律で定められた届出義務者(親族、同居者、家主など)。一般的にはご遺族の代表者が行います。
いつまでに提出する?
• 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)と定められています。期限を過ぎると理由書の提出や過料が科される場合があるため注意が必要です。
どこへ提出する?
• 以下のいずれかの市区町村役場(市役所、区役所、町・村役場)の戸籍担当窓口に提出します。1. 故人様の本籍地2. 届出人の所在地(現住所)3. 死亡した場所
葬儀の日程を決める上で火葬場の予約が必要不可欠ですが、火葬場の予約には「火葬許可証」が必要です。そのため、死亡届は速やかに提出するのが一般的です。
2:「火葬許可証」が交付される
死亡届を提出する際に、同時に「死体火葬許可交付申請書」(自治体により名称は異なります)を提出します。この申請書を提出することで、役所は「火葬許可証」を交付します。
この火葬許可証がなければ、法律上、火葬を行うことができません。非常に重要な書類です。
ほとんどの葬儀では、この死亡届の提出から火葬許可証の受け取りまでの一連の手続きを、葬儀社が代行してくれます。ご遺族は死亡診断書と印鑑を葬儀社の担当者に渡すだけで、あとは任せることができます。
3:火葬場で「火葬許可証」を提出する
役所で交付された「火葬許可証」は、火葬当日に必ず火葬場へ持参し、職員に提出しなければなりません。これを忘れてしまうと、いかなる理由があっても火葬を行うことができません。
葬儀社の担当者が責任を持って管理し、提出まで行ってくれるのが一般的ですが、万が一に備え、ご遺族も書類が確かに火葬場へ渡されたことを確認しておくとより安心です。
4:火葬後に火葬執行済の印が押され「埋葬許可証」となる
火葬が無事に終わると、提出した「火葬許可証」が返却されます。しかし、ただ返ってくるわけではありません。
火葬場の管理者が「火葬執行済」といった内容の証明印(スタンプ)を押してくれます。この印が押された瞬間から、「火葬許可証」は「埋葬許可証」へとその名を変え、法的な効力も「遺骨をお墓に納める(埋葬・埋蔵)ことを許可する」ものに変わります。
この「埋葬許可証」は、ご遺骨が収められた骨壷の箱(桐箱など)の中に一緒に入れて渡されるのが一般的です。これで、納骨の準備が整ったことになります。
それぞれの許可証はいつ必要?役割と提出先を整理
「火葬許可証」の段階と「埋葬許可証」の段階で、それぞれいつ、どこで、何のために必要になるのかを整理しておきましょう。
「火葬許可証」が必要な場面:火葬当日
• 役割:故人様のご遺体を火葬することを法的に許可する証明書です。
• 必要なタイミング:火葬を行う当日。
• 提出先:火葬場の管理事務所や受付。
• 注意点:この書類がなければ火葬は絶対にできません。紛失しないよう、葬儀社の担当者と共に厳重に管理する必要があります。
「埋葬許可証」が必要な場面:納骨時
• 役割:火葬されたご遺骨を、お墓や納骨堂などに納めることを法的に許可する証明書です。
• 必要なタイミング:お墓などに納骨を行う日。四十九日法要や一周忌などのタイミングで行うことが多いですが、時期に決まりはありません。
• 提出先:お墓や納骨堂の管理者。具体的には以下のような場所です。
・ 公営・民営霊園の管理事務所
・ 寺院墓地のご住職
・ 納骨堂の管理者
・ 樹木葬霊園の管理者 など
• 注意点:この書類がなければ納骨はできません。管理者は、埋葬許可証を受け取ることで、誰の遺骨が、いつ、どこに納められたかを記録・管理します。
埋葬許可証を再発行するには
納骨までの間に、誤って埋葬許可証を捨ててしまったり、どこに保管したか分からなくなったりするケースは、残念ながら少なくありません。しかし、ご安心ください、埋葬許可証は再発行が可能です。手続きの窓口は、自治体によって若干異なりますが、基本的には以下の2パターンのどちらかになります。
パターンA:火葬許可証を発行した市区町村役場で再発行する
これが最も一般的な方法です。紛失に気づいたら、最初に死亡届を提出した市区町村役場(市役所)の戸籍担当課に連絡し、再発行手続きについて確認してください。「埋葬許可証の再発行は市役所」と覚えておきましょう。
再発行手続きに必要なもの(一般的な例)
• 死体火葬許可証再交付申請書:役所の窓口にあります。
• 申請者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
• 申請者の印鑑(シャチハタ不可)。
• 手数料:1通300円〜400円程度(自治体により異なります)。
• 故人様と申請者の関係がわかる戸籍謄本など:申請者が死亡届の届出人でない場合に必要となることがあります。
誰が申請できる?
• 死亡届の届出人、故人の配偶者、直系血族(父母、子、孫など)が一般的です。それ以外の方が申請する場合は、委任状が必要になることが多いです。
役所での書類保管期間は、法律で5年間と定められていることがあります。5年以上経過している場合、役所での再発行が難しくなり、後述のパターンBの方法を取る必要があります。
ただし、自治体によっては長期間保管している場合もあるため、何年経っていても、まずは役所に問い合わせるのが最善です。
パターンB:火葬を行った火葬場で「火葬証明書」を発行してもらう
役所での再発行が困難な場合や、自治体の指示があった場合は、実際に火葬を行った火葬場に連絡します。火葬場では「埋葬許可証」そのものではなく、「火葬執行済証明書」や「火葬証明書」といった名称の、火葬を執り行ったことを証明する書類を発行してもらえます。「火葬執行済証明書」や「火葬証明書」といった名称の、火葬を執り行ったことを証明する
この「火葬証明書」が、埋葬許可証の代わりとして法的に認められており、納骨時に使用することができます。
• 手続きに必要なもの:火葬場によって異なりますので、必ず事前に電話で確認してください。故人の氏名、死亡年月日、火葬年月日などを正確に伝える必要があります。
どちらのパターンになるか分からない場合も、まずは「死亡届を出した市役所に電話で相談する」ことから始めましょう。
お墓の引っ越し(改葬)でも埋葬許可証は必要?
お墓の引っ越しである「改葬」の際には、元の埋葬許可証をそのまま使うわけではありません。改葬専用の手続きを行い、「改葬許可証」という新しい許可証を取得する必要があります。
改葬手続きの簡単な流れ
1. 新しいお墓を決める:引越し先の墓地管理者から「受入証明書(永代使用許可証など)」をもらう。
2. 現在の墓地管理者に連絡:現在の墓地管理者から「埋蔵証明書」を発行してもらう。
3. 役所で申請:現在の墓地がある市区町村役場で、「改葬許可申請書」「受入証明書」「埋蔵証明書」を提出し、「改葬許可証」を交付してもらう。
4. 遺骨の取り出し:現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出す。
5. 新しいお墓へ納骨:新しい墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨する。
このように、改葬の場合は「埋葬許可証」ではなく「改葬許可証」が納骨時に必要な書類となります。
埋葬許可証の正しい保管方法
埋葬許可証の再発行は可能ですが、時間も手間もかかり、ご遺族に余計な負担をかけてしまいます。火葬場で受け取ってから納骨の日まで、大切に保管しましょう。
推奨される保管場所は以下の通りです。
• 骨壷が入っている桐箱の中:最も一般的で、遺骨とセットで管理できるため紛失しにくい方法です。火葬場で渡される際に、多くは箱の中に一緒に入れてくれます。
• 仏壇の引き出し:ご自宅に仏壇がある場合は、引き出しの中など決まった場所に保管するのが良いでしょう。
• 重要書類をまとめているファイルや金庫:他の重要書類と一緒に保管することで、誤って捨ててしまうリスクを減らせます。
どこに保管した場合でも、最も大切なのは「家族間で保管場所を共有しておくこと」です。誰か一人しか知らない状態だと、その人が忘れてしまったり、万が一のことがあったりした場合に、他の家族が困ってしまいます。「埋葬許可証は〇〇にしまってあるからね」と、必ずご家族に伝えておきましょう。
よくある疑問
「最終的に火葬場で受け取る」となります。火葬場で火葬が終わった後、その「火葬許可証」に執行済の印が押されます。証明印が押された「埋葬許可証」を、ご遺骨と一緒に火葬場で受け取ります。
「埋葬許可証の有効期限」についてですが、法律上の有効期限は一切ありません。
紛失してしまった場合は、埋葬許可証は再発行が可能です。火葬許可証を発行した市区町村役場で再発行してもらいましょう。
まとめ
ご遺族にとって、葬儀前後の手続きは心身ともに大きな負担がかかります。しかし、一つひとつの手続きの意味や流れを正しく理解しておけば、不安は大きく軽減されるはずです。
もし手続きの途中で分からないことが出てきたら、遠慮なく葬儀社の担当者や、役場の職員、霊園の管理者に相談してください。きっとあなたの助けになってくれるはずです。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、故人様を安らかにお見送りするための一助となれば幸いです。