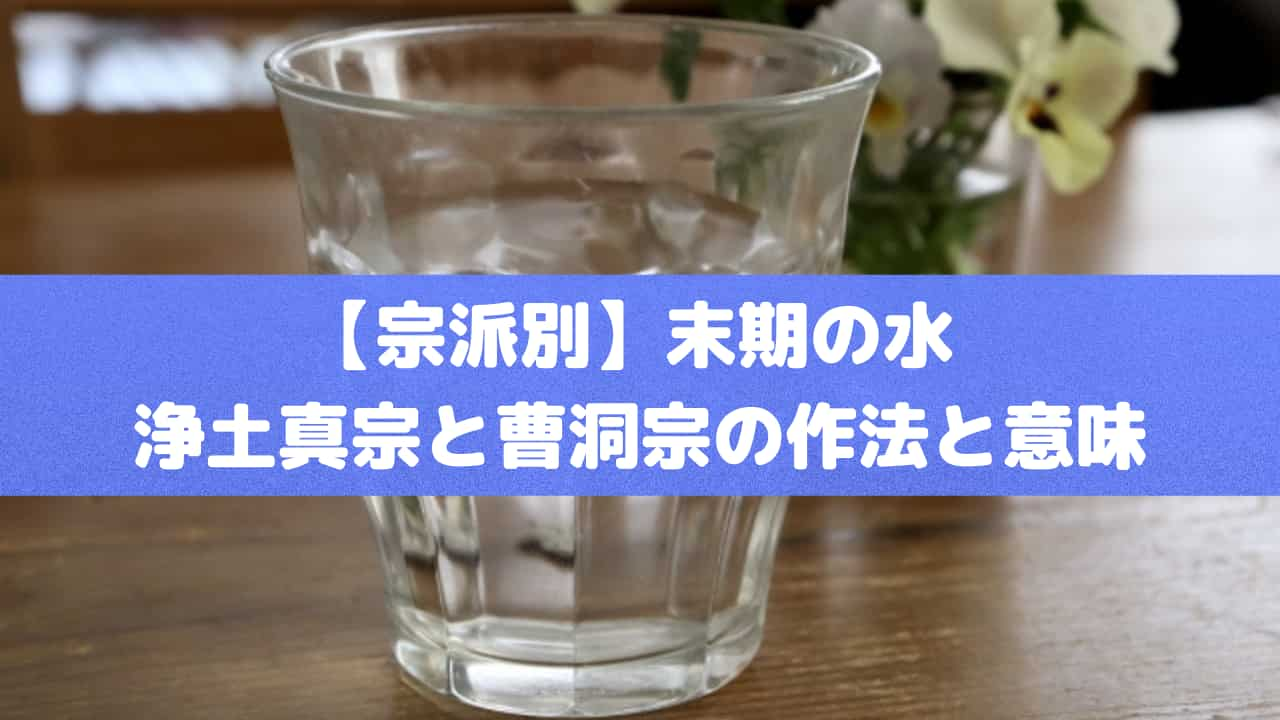この記事では、「末期の水とはそもそも何なのか」という基本的な知識から、「末期の水 浄土真宗」における考え方と対応、そして「末期の水 曹洞宗」における意味合いと具体的な作法について、詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
それぞれの宗派が大切にしている教えに触れながら、なぜそのような違いが生まれるのか、その背景にも光を当てていきます。いざという時に慌てず、故人と心静かに向き合うための一助となれば幸いです。
末期の水とは
末期の水(まつごのみず、「死に水」とも)とは、臨終に際して、または亡くなられた直後に、故人の口を水で潤す日本の伝統的な儀式です。一般的には、故人が安らかにあの世へ旅立てるように、そして喉の渇きを癒すためといった願いが込められています。
筆やガーゼ、あるいは樒(しきみ)の葉などに水を含ませて、故人の唇を軽く湿らせるように行われることが多いです。この行為の背景には、故人への最後のいたわりや、冥福を祈る心が深く関わっています。
浄土真宗における末期の水
浄土真宗は、他の多くの仏教宗派とは異なる独自の死生観を持っているため、末期の水の捉え方にも大きな特徴があります。
浄土真宗の教義の核心(阿弥陀仏の絶対他力と即得往生)
浄土真宗の教えは、宗祖である親鸞聖人(しんらんしょうにん)によって開かれました。その核心は、阿弥陀仏(あみだぶつ)という仏様の「本願力(ほんがんりき)」を信じること、ただそれだけで、どのような人であっても臨終と同時に阿弥陀仏の浄土(極楽浄土)に往生(おうじょう:生まれ変わること)し、仏になることができるというものです。
これを「他力本願(たりきほんがん)」と言い、自らの修行や善行(自力)によって悟りを開くのではなく、全てを阿弥陀仏の力にお任せするという立場です。
特に重要なのが「即得往生(そくとくおうじょう)」あるいは「臨終即往生(りんじゅうそくおうじょう)」という考え方です。
これは、阿弥陀仏を信じ、「南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)」と念仏を称える者は、この世の命が終わるその瞬間に、何の隔てもなく、時間をおかずに直ちに浄土に生まれ、仏としての悟りを開く(成仏する)とされています。
つまり、死は終わりではなく、浄土での新たな始まりであり、しかもそれは阿弥陀仏によって完全に保証されているのです。
この世で迷いの存在であった凡夫(ぼんぶ:普通の人々)が、死と同時に仏になるという、非常にダイナミックで希望に満ちた教えと言えるでしょう。
この「即得往生」の教えがあるため、浄土真宗では原則として末期の水を行いません。
なぜ浄土真宗では末期の水を基本的に行わないのか

1.すでに仏様になっているため
浄土真宗の門徒(信者)は、亡くなった瞬間に阿弥陀仏の浄土に往生し、仏となっています。仏様には、喉の渇きも苦しみもありません。
したがって、現世の人間が故人のために喉を潤したり、安らかな旅立ちを助けたりする意味での末期の水は、その必要性がないと考えられています。仏に対して人間が何かしてあげる、という構図自体が成り立たないのです。
2.儀式ではなく信心が往生の要
浄土真宗では、往生の条件は阿弥陀仏への「信心(しんじん)」ただ一つです。末期の水のような儀式を行ったかどうかで、故人の往生が左右されることは一切ありません。
親鸞聖人は、形式的な儀礼や迷信にとらわれることを厳しく戒めました。大切なのは、阿弥陀仏の救いを疑いなく信じる心であり、それ以外の行いは往生には影響しないのです。
3.死を「穢れ」と捉えない思想
一部の宗教観や古い習俗では、死を不浄なもの、穢れたものと見なすことがありますが、浄土真宗ではそのような捉え方をしません。
死は、阿弥陀仏の光明に摂め取られ、浄土という清浄な世界に生まれる尊い転機です。したがって、死の穢れを清めるという意味合いで末期の水を行う必要もありません。
4.親鸞聖人の教えの革新性
親鸞聖人が活躍した鎌倉時代は、多くの人々が複雑な修行や儀礼なしには救われないと考える風潮がありました。その中で親鸞聖人は、阿弥陀仏の慈悲は全ての人に平等に注がれており、ただ信じるだけで救われるという「絶対他力」の教えを打ち出しました。
これは当時としては非常に革新的な思想であり、既存の儀礼中心の仏教観からの大きな転換を意味していました。末期の水を行わないというのも、この徹底した他力思想の表れの一つと言えます。
このように、「末期の水 浄土真宗」における対応は、阿弥陀仏の絶対的な救いを信頼し、故人がすでに仏となっているという確信に基づいています。これは、故人への思いやりがないのではなく、むしろ故人の最も幸福な状態(成仏)を信じているからこその姿勢なのです。
例外的に行うケースとその心情的背景
原則として浄土真宗では末期の水は行いませんが、ごく稀に例外的に行われる場合があります。これは教義上の理由というより、ご家族の切実な気持ちに寄り添うという配慮によるものです。
例えば他宗派に慣れ親しんだご家族の希望、地域の慣習との調和、故人が生前大切にしていたという理由、また病院や葬儀社から一般的な仏式の作法として案内された場合もあります。
とは言え、浄土真宗の僧侶も門徒も、この儀式が往生に影響するものではないという教義上の立場を守って臨みます。
曹洞宗における末期の水
曹洞宗は、道元禅師(どうげんぜんじ)と瑩山禅師(けいざんぜんじ)を両祖と仰ぐ禅宗の一派です。坐禅を修行の中心としながらも、葬儀や故人への供養も非常に丁寧に行う宗派であり、末期の水に関しても、浄土真宗とは異なる考え方と確立された作法があります。
曹洞宗の教義の要点

曹洞宗は「私たちの心そのものが仏」であるという教えに基づき、坐禅という実践によって本来備えている仏性に気付き、仏として生きる道を歩みます。また「修行」と「悟り」を分けないという考えも大切にしており、坐禅こそ仏の姿そのものです。
葬儀においても「授戒」と「引導」を行うことで、故人が仏弟子となって安らかに悟りの世界へ旅立てるように導きます。
• 授戒
故人に仏弟子としての戒を授け、仏門に入る儀式です。これにより、故人は正式に仏の道を歩む者となります。
• 引導
導師(僧侶)が法語や松明(たいまつ、現代では象徴的なもの)を用いて、故人を仏の悟りの世界へと導く儀式です。故人が迷うことなく仏道を進めるように導きます。
なぜ曹洞宗では末期の水を行うのか
曹洞宗において末期の水を行うのは、単なる慣習ではなく、仏教的な意義と故人への深い思いやりに根差しています。
1.故人の苦しみを和らげる慈悲の心
臨終を迎えるにあたり、故人は肉体的な苦痛や喉の渇きを感じているかもしれません。その渇きを潤し、少しでも苦しみを和らげてあげたいという、人間としての自然な情愛、仏教でいうところの「慈悲の心」の表れです。
2.お釈迦様の故事に倣う
仏教の開祖であるお釈迦様(釈迦牟尼仏)が入滅(亡くなること)される際に、弟子の一人である阿難(あなん)尊者がお釈迦様の渇きを癒すために水をお供えしたという故事があります。この故事に倣い、仏弟子として旅立つ故人に対しても、同じように水を手向けるという意味合いがあります。
3.身と心を清める浄化の儀式
水には古来より浄化の力があるとされています。末期の水には、故人の口を清め、ひいては身心を清浄にして、新たな仏としての旅立ちに備えるという意味も込められています。
4.仏弟子としての旅立ちの準備
前述の授戒や引導といった儀式によって、故人は仏弟子となります。末期の水は、その仏弟子としての新たな門出に際して、現世からの最後の手向けであり、送り出す側の清らかな気持ちを伝える行為とも言えます。
5.遺族のグリーフケアとしての役割
末期の水を行うことは、遺された家族が故人との最後の触れ合いを通じて、死という現実を徐々に受け入れ、悲しみを乗り越えていくための大切なプロセスの一部となり得ます。故人のために何かをしてあげられたという実感は、心の慰めにも繋がります。
末期の水:他の主な仏教宗派では
浄土真宗を除き、多くの仏教宗派では、曹洞宗と同様に末期の水を行うのが一般的です
天台宗・真言宗(密教系)
これらの宗派でも、故人の口を水で潤す儀式は行われます。特に真言宗では、光明真言(こうみょうしんごん)を唱えながら、印を結んで行うなど、宗派独特の密教的な作法が見られることがあります。
故人の即身成仏(この身このままで仏になること)や、大日如来の光明の世界への導きを祈る意味合いが込められています。
日蓮宗
日蓮宗でも、末期の水は行われます。「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えながら、故人の安らかな霊山浄土(りょうぜんじょうど:日蓮宗における理想の仏国土)への旅立ちを願って行われることが多いです。
臨済宗(禅宗系)
曹洞宗と同じ禅宗である臨済宗でも、一般的に末期の水は行われます。作法や意義については曹洞宗と共通する部分が多いですが、細部は各寺院や流派によって異なることもあります。故人が仏性を現し、安らかに仏の世界へ赴くことを願います。
末期の水を行わなかった場合、故人に不利益は?
浄土真宗の場合
教義上、末期の水は故人の往生に一切影響を与えません。阿弥陀仏の救いは、人間が行う儀式の有無によって左右されるものではないと固く信じられているからです。
したがって、行わなくても全く問題はありませんし、故人に何らかの不利益が生じることもありません。
曹洞宗や他の多くの宗派の場合
末期の水は、故人への思いやりや供養の一環として、また仏教的伝統として大切な儀式と位置づけられています。しかし、絶対不可欠な条件ではなく、これを行わなかったからといって故人が成仏できない、あるいは不幸になるといった考え方はしません。
様々な事情(急な逝去、医療的な制約など)で行えなかったとしても、そのことを過度に悔やむ必要はありません。最も大切なのは故人を思う心であり、その後のご供養(読経、お焼香、お墓参りなど)を心を込めて行うことで、故人の冥福を祈ることは十分に可能です。
故人の宗派が分からない場合
故人の宗派が不明な場合、末期の水を行うかどうか、また行う場合の作法については非常に慎重な判断が求められます。
1.宗派の確認を試みる
親族や故人と特に親しかった友人・知人に尋ねてみる。古い仏壇があれば宗派を示すものがないか確認する。過去帳や古い葬儀の記録が残っていないか探してみるなど、できる範囲で宗派を確認する努力をしましょう。
2.無理に特定の作法で行わない
宗派が不明なまま、憶測で特定の宗派の作法(例えば、一般的な仏式として末期の水を行うなど)を強行するのは避けた方が賢明です。もし故人が浄土真宗の門徒であった場合、末期の水は教義にそぐわない行為となる可能性があります。
3.葬儀社に正直に相談する
経験豊富で信頼できる葬儀社であれば、このようなケースでの一般的な対応や、各宗派への配慮について適切なアドバイスをくれるはずです。無宗教形式でのお見送りも一つの選択肢として検討できます。
4.故人の遺志を最大限尊重する
もし故人が生前に、宗教的な儀式に関する何らかの意向(例えば「特定の宗教儀式はしないでほしい」「簡素にしてほしい」など)を示していた記録や記憶があれば、それを最優先に尊重すべきです。
まとめ
大切な方を亡くすという経験は、言葉では言い尽くせないほど深く、悲しいものです。その中で行われる末期の水は、行う宗派にとっては故人への最後の具体的ないたわりであり、遺された人々の心を慰め、故人との絆を再確認するための貴重な時間となり得ます。
しかし、どのような宗派であっても、最も重要なのは形式そのものに過度にとらわれること以上に、故人を心から思う気持ち、生前の感謝の念、そして安らかな旅立ちを願う純粋な祈りの心です。
宗派による考え方や作法の違いを理解し、それを尊重することは、故人にとっても、そして見送るご遺族にとっても、より心穏やかで悔いのないお別れを迎えるために不可欠と言えるでしょう。
もし、ご自身の家の宗派の作法や、臨終に際しての具体的な対応について分からないこと、あるいは心に抱える不安なことがあれば、決して一人で悩まず、まずは菩提寺の僧侶や、経験豊富な葬儀社の専門家に遠慮なく相談してください。彼らはきっと、あなたの心に親身に寄り添い、その状況に応じた適切なアドバイスとサポートを提供してくれるはずです。
この記事が、いつか訪れるかもしれないその大切な時のために、皆様の知識の一助となり、少しでも心の準備にお役立ていただければ、これほどうれしいことはありません。故人との最後のひとときが、温かく、敬意に満ちた、そして心に残るものとなりますよう、心よりお祈り申し上げます。